FIREを実行する方も含めて、会社を辞める方にとって、退職金の受け取り方は非常に重要な選択肢です。 会社によって退職金の取り扱いの制度が異なるため、すべての方が当てはまらない場合もありますが、「一括受け取り」「年金受け取り」が選択できる場合、受け取り方によって手取り額が大きく変わることも。
今回は、私が実際に悩んだ「年金の受け取り方」について、シミュレーションを交えながら記事にしてみました。
はじめに
私の勤めていた会社ですが、退職給付の仕組みが、
- 2割を、企業型確定拠出年金(DC: Defined Contribution Plan)で運用
- 8割を、確定給付企業年金(DB:Defined Benefit Plan)で運用
- 一時金として一括受け取り
- 年金として65歳から5年間確定年金
- 一時金と年金のミックス(割合は自由に選べない、数パターンから選択)
という仕組みになっていました。
そして、会社から
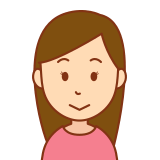
「モンチさん、退職金の受取り方法、
一括にするか年金にするかミックスするか考えておいてくださいね」
と選択を迫られるのです。
(補足:ちゃんと事前に退職制度の説明はありましたよ・・・)
一括受け取り(一時金) VS 年金受け取り
退職金の一括受け取り(一時金)と年金受け取り(分割)の最も重要な違いは、「税制上の優遇措置」です。
また、年金受取は「雑所得」として扱われ、国民健康保険料や介護保険料の算定対象になります。つまり、税金だけでなく、社会保険料も増える可能性が高いのです。
| 受取り方 | 所得 区分 | 適用される 控除 | 課税方法 | 社会保険料への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 一括 | 退職所得 | 退職所得控除 | 〇分離課税 ※退職金以外の税金に影響がでない | 〇なし |
| 年金 | 雑所得 | 公的年金等控除 | ×総合課税 ※他の所得と合算されて影響がでる | ×あり 国民保険などが上がる可能性あり |
一括(一時金)は「退職所得控除」で大きく優遇
一時金として受け取った退職金は「退職所得」となり、「退職所得控除」という強力な優遇措置が適用されます。
勤続年数が長いほど控除額が増えるため、長年勤めた方ほど税金がかかりにくい仕組みになってます。
国税庁のホームページにて詳細を確認することができます。
1. 退職所得控除の具体的な計算
| 勤続年数 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(※最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年) |
私の場合、28年と10か月の間、勤務していました。勤続年数は切り上げで考えますので、29年とすると、
800万円 + 70万円 x (29年 - 20年) = 1430万円
つまり、1430万円を超える部分について、税金を考える必要があります。
2.課税対象額(退職所得)の計算
税金がかかる金額(課税退職所得金額)は、退職金総額から上記の控除額を差し引いた後、さらに2分の1にするという優遇措置が適用されます。
税金の掛かる金額 = (退職金総額 − 1で求めた控除額) ÷ 2
私の場合、2000万円ほど退職金(DB部分)をもらえましたので
(2000万円 - 1430万円) ÷ 2 = 285万円
つまり、285万円に対して税金を納める必要があります。
3.課税金額の計算
2の税金の掛かる金額に対して、所得税や住民税がかかります。
所得税は、給与などと同じ累進課税(5~45%)、住民税は一律10%となります。
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 0円 ~ 195万円 | 5% | 0円 |
| 195万円 ~ 330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円 ~ 695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円 ~ 900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円 ~ 1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円 ~ 4000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円 ~ | 45% | 4,796,000円 |
私の場合であれば、285万円に税金がかかります(細かいところは割愛)ので、
・所得税(10% − 控除9万7500円): 285万円 × 10% − 97,500円 = 187,500円
・復興特別所得税: 187,500円 × 2.1% ≒ 3,973円
・住民税(10%): 285万円 × 10% = 285,000円
合計の約48万円 が、納めるべき税金の額となります。
年金受け取りは「公的年金等控除」で優遇される
退職金を年金形式で受け取る場合は、「雑所得」として扱われます。雑所得には「公的年金等控除」が適用され、こちらも税制上の優遇措置が設けられています。
注意すべきところは、厚生年金・国民年金や、個人で契約している積立保険などの私的年金どがあれば、その金額と合算して、税金を考える必要があります。
1. 公的年金等控除の計算
年金受給者の年齢と年金収入額に応じて、以下のような控除額が設定されています。
下は、年金以外の所得が1,000万円以下のケースです。
(1000万円を超える場合は、また違う計算式になります)
| 受給者の年齢 | 年金額(公的年金等の受給額) | 公的年金等控除額 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 330万円未満 | 110万円 |
| 330万円以上 410万円未満 | 年金額×25%+27万5,000円 | |
| 410万円以上 770万円未満 | 年金額×15%+68万5,000円 | |
| 770万円以上 1,000万円未満 | 年金額×5%+145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 195万5,000円 | |
| 65歳未満 | 130万円未満 | 60万円 |
| 130万円以上 410万円未満 | 年金額×25%+27万5,000円 | |
| 410万円以上 770万円未満 | 年金額×15%+68万5,000円 | |
| 770万円以上 1,000万円未満 | 年金額×5%+145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 195万5,000円 |
私の場合であれば、2000万円ほど退職金(DB部分)を65歳から5年給付の選択となりますので、1年あたり400万円をもらうことができます。
今回、厚生年金などの公的年金は考えないとして、退職金の受け取りのみとした場合、
公的年金等控除額は、
400万円 × 25% + 27万5000円 = 127万5000円
2. 課税対象額(雑所得)の計算
課税対象となる雑所得は、年金収入から公的年金等控除を差し引いた金額です。
課税雑所得金額 = 年金収入 − 公的年金等控除
私の場合、
400万円 - 127万5000円 = 272万5000円
年金受け取り中の5年間、毎年272.5万円に対して税金を納める必要があります。
3. 課税金額の計算
こちらは、先に説明した退職金一括支払いの時と同じ計算方法となります。
ただし、注意すべき点として、退職金一括受け取りの場合は、分離課税のため他の所得に影響を及ぼしませんが、年金受け取りの場合は、毎年の所得として扱われるため、他の収入(例えば配当金や不動産収入など)と合算される点も考慮しておく必要があります。
私の場合であれば、272.5万円に税金がかかります(細かいところは割愛)ので、
・所得税(10% − 控除9万7500円): 272.5万円 × 10% − 97,500円 = 175,000円
・復興特別所得税: 175,000円 × 2.1% ≒ 3,675円
・住民税(10%): 272.5万円 × 10% = 272,500円
合計の約45万円 が、毎年納めるべき税金の額となります。(5年間)
まとめ
勤続年数が長い人ほど、退職所得控除が大きくなるため、一括受取りがかなり有利なことがわかりました。 また、一括受取りは、分離課税となるため、他の所得への影響、国民健康保険等への影響がないこともメリットになると思います。
あとは、一括受取りと年金受け取りを併用した場合に、どのように税金になるかを検討する必要があると思いますが、それについては、次回の記事にて・・・




コメント